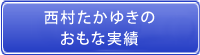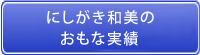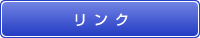子育ての支援を充実するという制度と共に、大きな理念の一つに、就学前の子どもたちを保育、教育で分けることなく一体化していく、ということがあります。とはいうものの、これまで、厚労省と文科省という二つの省がそれぞれ管轄していた制度を一つにする、ということは想定以上に大変なようです。
制度の一つとして、利用したい人はまず「保育の必要性」の認定を市町村から受け、認定されたら原則、全員が利用できる仕組みに変わります。しかし現実は、施設の定員以上の需要がある場合は、やはり待機となってしまいます。
二つ目は、保育を利用できる要件が広がり、パート勤務や在学中の人なども対象となり、その状態に合わせて保育の利用の時間が11時間と8時間との2つのパターンでの保育の認定となります。
そうして上記のことを実現するために、保育の定員や種類が増えます。草津市も、0~2歳児が対象の「小規模保育」(定員19人)の新たな保育施設を導入し、H27年度からスタートします。そのほとんどの施設が新たに建てるのでなく、マンションやビルの一階スペースとなるようです。
家庭で子育てする人への支援も増えます。草津市も子育てコンシェルジュという方を採用する予定で、各種の情報提供や子育て相談を受けます。
スタートの段階では、大きな変化を実感することはないかもしれませんが、各自治体の知恵比べともなり、子育て支援にじわじわと差がついてくると思われます。草津市においては、今のところ国の標準レベルでのスタートですが、今後議会としても積極的に課題の発見やニーズの把握に努めていきたいと思います。